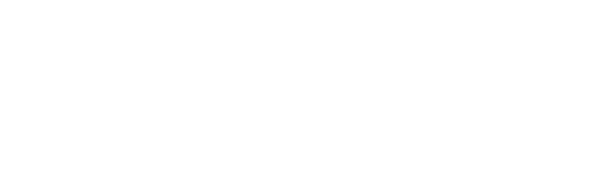人々のファッションは次々に移り変わり、時代によってトレンドは全く違いますが、それは昔も同じで、時代背景によって服飾は変わっていきました。昔の時代にダンディズムという概念はありませんが、それとよく似た、特に武士には武士としての心構えを身だしなみで表現していました。そしてそれに伴い、身に付けるアイテムにもこだわりを見せました。今回は武士のファッションアイテムを見ていきます
目次
1. 戦場におけるファッションアイテム
1-1.当世具足
1-2.陣羽織
2.刀装具
3. 印籠
4. 根付
5.最後に
1.戦場におけるファッションアイテム
1-1.当世具足
戦国時代も末期になり、新しい兵器である鉄砲が登場すると、甲冑も源平の時代から着用していた総重量30㎏にもなる「大鎧」よりもより頑丈で動きやすい実用性が求められました。そこで作られたのが「当世具足」です。
「当世」とは現代という意味で、「現代風の甲冑」ということですね。
当世具足の進化した一番の見どころは胴の部分で、それまで小札(こざね)と呼ぶ鉄や革で出来た小さな板を紐で縦横に縫い合わせていましたが、非常に手間のかかるものでした。そこで鉄の一枚板である板札(いたざね)を使い、より防御力が増した上、大量生産向けになりました。
また、合戦の規模が集団戦となって拡大したことにより、遠目でも敵味方の識別がしやすいように、奇抜な甲冑が登場しました。武将達は兜に様々な個性あふれる大立物を付けました。
兜は「兜首」という言い方があるように、あるランク以上の者しかかぶれないものでした。兜の前立てに奇抜なものを付けている兜を「変わり兜」と呼び、有名な変わり兜を挙げると、前田利家の鯰の尾形、加藤清正の長烏帽子形、上杉謙信の三宝荒神形、黒田長政の一の谷形、伊達政宗の半月型など各々が自分の好みを表現していました。
変わり兜には神仏の形を表したものが多く、それだけ武将達が神仏と真剣に向き合っていたことがわかります。直江兼続の有名な「愛」一文字の兜は、愛情の愛だと思われがちですが、愛染明王の愛だそうです。
敵味方の識別がしやすいという他に、戦場で活躍してもそれが誰なのかわからなければアピール出来ませんが、変わり兜をかぶっていればすぐに名前を憶えてもらえるという理由もあったのです。
1-2.陣羽織
戦国乱世の世を生き抜いた武将たちは、大立物と呼ばれる奇抜な鎧兜で自らを着飾り、また戦場において目印となりましたが、陣羽織もまた、戦場の中で彼らを目立たせたファッションアイテムです。
陣羽織が作られた背景には、16世紀半ばから始まった南蛮貿易があり、鉄砲、キリスト教、眼鏡や時計、カステラなどの食品と共に、ヨーロッパの服飾技術が初めて持ち込まれました。陣羽織はマントを参考にしたものだと言われています。
現代の服には当たり前であるボタン留めや立て襟、曲線裁ちといった裁縫技術はこの時初めて登場しました。
武将達は南蛮人から仕入れた異国の染織品をふんだんに使い自らを装いました。特に、羊毛などを用いて表地を起毛させたラシャは、厚手で防水、防寒に優れ、さらに色彩も鮮やかで、武将達はラシャを好みました。他にも、木綿の生地に花、鳥獣、人物などを多色で染め出した「更紗(さらさ)」、ビロードなども使われ、武将それぞれの個性や思想、美意識を表し、また高級な素材を使うことで自分の財力や存在感を見せつけたのでした。
豊臣秀吉の着用した「鳥獣文様陣羽織」は高級ペルシャ絨毯をそのまま陣羽織に仕立てた大胆なものです。表地の文様はペルシャの伝統的な文様で、ライオンやクジャクといった当時日本にはいなかった動物が描かれています。
伊達政宗の「紫羅背板五色水玉文様陣羽織」も有名です。これは大小異なる青、赤、黄、緑、白をバランスよく配置された水玉模様が特徴で、戦国のおしゃれ番長、伊達政宗のセンスが光ります。
戦場では武将達によるおしゃれ着合戦も繰り広げられていたのでした。
2.刀装具
室町時代の後期、槍や鉄砲の台頭により馬上戦より徒歩戦が重要視され、それに伴い武士の腰物も太刀から打刀(うちがたな)へと変化しました。
打刀の外装を拵え(こしらえ)と言いますが、武将達は打刀と一揃いの脇差を合わせた大小拵えを服飾の一部とし、華美を装った拵えが好まれるようになりました。
装剣金工にもこだわりを見せ、繊細巧緻な美を展開させました。
拵えの中でも彫金加飾を施したものには、鍔、縁、頭、目貫、小柄、笄などがありますが、江戸時代にはそれらを拵えから分離し、三所物(みところもの)や五所物(いつところもの)と称して鑑賞する風習が広まります。それにより彫金技法の発達が進み、江戸時代美術のひとつの特色として取り上げられています。
足利義政に仕えた後藤祐乗から始まる後藤家は、刀装具の彫金を家業とし明治の廃刀令まで将軍家や大名の拵えを飾り、後藤家一派の作品は「家彫(いえぼり)」と呼ばれました。
後藤家の刀装具は格式が高く、伝統を重んじ技法の自由さには制限がありました。そこで江戸時代中期に登場したのが、横谷宗珉に始まる町職人達の一派である「町彫(まちぼり)」です。町彫の職人達は家彫に対抗して自由で斬新な作品を多く残しました。
刀装具は、刀の外装の一部の小さい枠の中で動物、風景、人物その他様々な表現がなされている武士達自慢のファッションアイテムです。
3.印籠
印籠と聞いて浮かぶイメージといえば、テレビ時代劇「水戸黄門」で悪党に見せつけている印象が強いと思いますが、本来の使い方は常備薬を入れるための携帯用薬入れで、16世紀後半から普及し始め、武士や裕福な町人が肌身離さず携帯していました。
しかし江戸時代中期になり戦もなく平和な世の中になると、印籠は薬入れとしてではなく、刀装具と同様武士の重要なファッションアイテムとなっていきました。
その結果職人達によって多種多様な印籠が生み出され、江戸時代を代表する美術工芸品となりました。
印籠は、三段から五段の扁平な小型の容器の両脇の穴に「印籠紐」を通した構造になっています。そして印籠全体に蒔絵、螺鈿(らでん)などの精巧な装飾が施されました。
その装飾は、江戸時代に存在した全ての工芸分野の技術が応用されており、名工による発想豊かな「変わり種」も多く、当初の素材であった和紙だけでなく、木、鉄、像牙などの素材も使われました。
しかし明治以降印籠は日本人の生活から姿を消していきます。今では海外のコレクターに人気で、国内の美術的価値の高い印籠がどんどん海外に流出し続けています。
日本では今年4月から6月にかけ、東京富士美術館で「サムライダンディズム展」が催され、刀装具と、230点もの印籠が展示されました。
その細かすぎる技巧が施された装飾は、単眼鏡やルーペが欠かせないほど見事なものです。
4.根付
根付(ねつけ)とは江戸初期に登場した装飾品で、印籠をはじめ煙草入れや巾着などの提物を持ち歩く時、落ちないように紐の先に結わえ帯に吊るして使う3~4㎝程度の留め具です。
当初は実用品として使用されていましたが次第に細工や彫刻に凝られるようになり、装飾品としての要素が強くなっていきました。武士から庶民までがお気に入りの根付を身に付け、ファッションアイテムとして江戸後期には爆発的に流行しました。
根付が根付であるための条件とは、実用的なサイズであること、丸いフォルムであること、紐を通すための穴が空いていること、そして手に取って眺めた時に、上下表裏どこから見ても作品として完成していることが挙げられます。
根付に使われる素材は、木材、動物の牙、陶磁器、金属、ガラスなど様々です。そこに彫られる題材は動物、妖怪、神様、人物、文化風俗と制限はなく自由で、職人の粋な遊び心が3~4cmに凝縮されています。
印籠同様、明治に入ってからは国内で作られなくなりましたが、海外では美術工芸品として評価が高く輸出用に生産されました。
平成に入ってから根付の高い芸術性が再び注目を集めており、「現代根付」が根付師達により制作されています
5.最後に
今回は武士のファッションアイテムについて書いてみました。昔の服装というと着物を着ているというざっくりした印象がありますが調べていくと、武士に限らず人々の服飾は時代によって特徴があり、どんどん変わっています。その中で、現代においても80年代、90年代と時代によって流行っていたものが全然違うようにその各時代で流行したファッションアイテムもあったのでした。
特に江戸時代になって平和になると、武士達は刀の刀装具にこだわったり、印籠なども本来の使い道だけでなくファッションとしても持ち歩いていたのです。江戸時代の吉原などでは、おしゃれな着こなしやアイテムもこだわって遊女にモテる武士や町人を「通人(つうじん)」、モテない人を「半可通(はんかつう)」と呼び男っぷりを競っていたようです。
私も印籠や根付がここまで見事な彫金を施された美術的工芸品だとは知りませんでした。今後美術館で展覧会があれば足を運びたいと思います。
江戸時代の「通人」「半可通」については今後もっと詳しく紹介いたします
【参考文献】
1、江戸のダンディズム 著者:河上 繁樹
2、戦国の合戦 著書:小和田 哲男